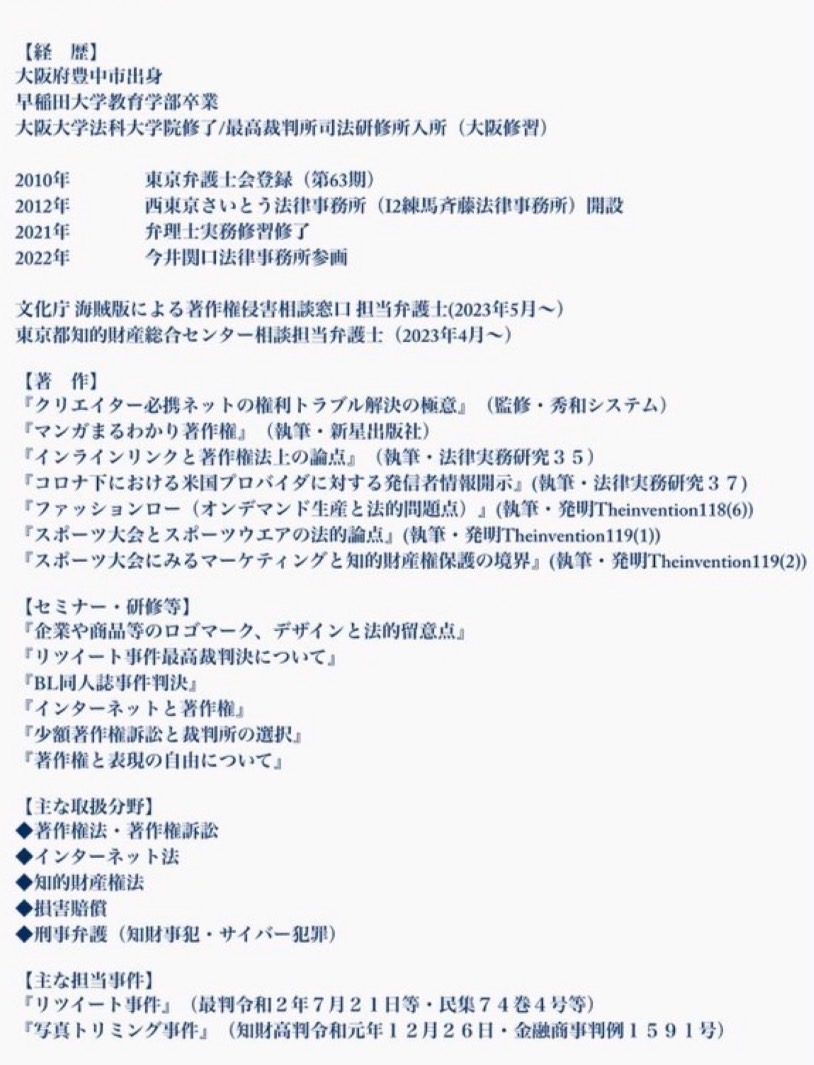①共犯の錯誤
正犯者の実行行為と、他の共同正犯者ないし、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことを、共犯の錯誤という。共犯者の認識した主観と、客観的に存在する事実のズレの問題であり、共犯者に故意を問えるかの問題である。
注1)共犯者と実行行為者の意図の食い違いの問題は、さらに同時に、共犯者と実行行為者が、犯罪を共同して行ったと評価できるかの問題も含んでいるというべきである。なぜなら、犯罪を共同して実行したと評価できるか否かの問題は、心理的相互利用補充関係による法益侵害への因果的寄与を除いては語れず、結局、共謀者間の主観に解消されるからである。
注2)これに対して、幇助者、教唆者については、主観の共有は重大な問題でなく、片面的教唆犯、片面的幇助犯も認められるから、単に故意の問題を生じるに過ぎない。
②共同正犯の錯誤
共謀にかかる犯罪事実の内容と右共謀に基づき実行された犯罪事実との間に食い違いがある場合である。
②-①具体的事実の錯誤
共謀時の対象と、実際に犯罪が実行された対象が、同一構成要件内で異なるような場合である。共謀のみに加担した者が、実際に実行された犯罪を「共同して…実行した」(60条1項)と評価でき、かつ、共謀のみに加担した者に「罪を犯す意思」(38条1項)が認められるかが、問題となる。この点、「共同して犯罪を実行」したと言いうるには、構成要件レベルまで抽象化された主観の共有で足り(部分的犯罪共同説)、また、構成要件レベルまで抽象化した事実の認識で規範の問題に直面したといえ、故意責任を問える(法定的符号説)。したがって、具体的事実の共同正犯の錯誤には、共同正犯が成立する。
②-②抽象的事実の錯誤
これに対して、抽象的な事実の錯誤に関しては、法定的符号説から、構成要件が重なり合う軽い限度で、故意が認められる。したがって、後はどの範囲で共同正犯が成立するかの問題になるが、共謀の成立に罪名の一致までは必要でなく、共有した主観のうち、重なり合う軽い罪の限度で、「共同して…実行した」(60条1項)ものと評しうるものと解する。
③加担犯の錯誤
加担犯の錯誤とは加担犯が加担行為時に認識していた事実と、実行された犯罪事実が食い違う場合をいう。加担犯の認識にかかわらず、加担行為と実際の実行行為に因果関係が認められる以上、客観的に幇助行為、教唆行為が行われたことは否定しえない。したがって、あとは、加担犯に故意を認めて、問責できるかの問題になる。
③-①具体的事実の錯誤
構成要件レベルまで抽象化された規範の問題に直面しているといえるから、実際の犯罪事実について、故意責任を問える。
③-②抽象的事実の錯誤
法定的符号説から、重なり合う軽い限度で、故意責任を問える。
④共犯形式相互間の錯誤
たとえば、主観的には精神的幇助行為の意図で、客観的には教唆行為を行ってしまったような場合である。実行行為に関する錯誤ではなく、自己の加担行為に関する錯誤である。この場合も、加担者は、主観の限度で規範の問題を乗り越えたといえるから、重なり合う軽い限度で、犯罪が成立する(38条2項参照)。
注1)主観的には教唆の意図で、客観的に間接正犯としての実行行為と評価される行為を行った場合も、教唆行為の規範の問題に直面しているにすぎず、教唆犯として問責されるにとどまる。
注2)反対に、主観的には間接正犯の意図で、被利用者の犯意を誘発してしまったような場合、被利用者はもはや道具とは評価できず、客観的には教唆行為を行ってしまったことになる。しかし、この場合も、間接正犯の故意は教唆行為の故意を包含していると解すべきであり、教唆行為について、間接正犯を犯す意思をもって、故意を肯定することはできると解すべきである。
注3)利用者が間接正犯の意図で利用行為をなした後、被利用者が、利用行為後に利用者の意図に気づき、被利用行為に出た場合、どう解すべきか。まず、間接正犯の実行行為は、利用者を基準に判定すべきであり、利用行為時に法益侵害結果の現実的危険性が認められれば、間接正犯の意図で間接正犯の実行行為を行い、その犯意を遂げたことになるから、間接正犯として問責できる。これに対して、被利用行為時に正犯者の不作為に基づく実行着手を観念する場合は、実行着手前に被利用者が自らの犯意を誘発しているから、利用者の行為に変容をもたらし、間接正犯の意図で教唆行為を行ったことになる。したがって、上記のとおり、間接正犯の故意は教唆の故意を包含するものとして、教唆犯として問責すべきことになる。